(下記シンポジウム前に書いたブログの改訂です)。
やや唐突だが,「咬み合わせ」に関する一般市民向けのかなり大規模なシンポジウムが開かれたこともあって(7月10日),密かに(?)研究してきた「咬み合わせと脳」について,ごく一部のデータを簡単に紹介したい。
咬み合わせを正しくすることを「咬合是正」といい,その療法を「咬合療法(occlusion-therapy)」という。
この療法は(やや極論だが)「万病を予防する」「万病を改善する」と言ってよいほどの効果を持つことが,多くの臨床例・実績で分かっている--ただし,こうしたことは,私の知る限り,丸山剛郎先生(阪大名誉教授)が開発した「丸山咬合療法」だけに関して言えることだが・・・。
(つまりは,丸山先生以外では丸山先生が設立したNPO法人日本咬合学会に所属している歯科医師の方々による咬合療法だけ,ということになる;ちなみに,私は歯科医師ではないくせに,この学会の特別会員ついで名誉会員として10年間も活動している・・・汗)。
通常の医療行為では,病気ごとに対症療法的な治療をすることが普通だが,咬合療法の場合,この療法だけで多数の病気を治療ないし改善,あるいは予防する,という特徴があって「東洋医学」に相似している。単一の方法で一点突破的に身体機能の全てを良くする,といった感じである。
これは,あくまでも丸山咬合療法を行なえる歯科医師に限るとはいえ,歯科のイメージ・守備範囲を根底から変えるように思える--歯科は虫歯の治療や歯列矯正などだけではないのだ。
これだけでも驚異的だが,さらに驚くのは,咬合療法は多くの病の予防・改善に留まらず,「若返り」にも効果があるらしいことだ。
端的に,咬合療法によって見かけの年齢が若くなるし,主観的にも若くなったと思う患者さんも多い--「見かけ年齢」が暦年齢よりも実年齢をより的確に表わすことが分かっているので(見かけ年齢が若いと,テロメアの長さも長いほど;e.g., Gunn et al., 2010),咬合療法によって身体が実際に若返えるとみなしてよいと思う。
このこと,特に「若返り」を,私は丸山先生との共同研究で,脳レベルで調べてきた経緯がある。「咬合療法によって脳は若返る」という仮説の下での研究である。
この際に注目したのは,「加齢に最も敏感で,非常に重要な高次脳機能」としてのワーキングメモリである(この脳機能の能力は人間性知能HQの中心的能力でもある)。
ワーキングメモリ能力は学業や社会生活(社会的成功・失敗などを含む),あるいは,各種精神疾患に深く関わり,かつ,年齢と共に(当然ながら個人差はあるが)ほぼ線形に低下する。認知症になるとワーキングメモリ能力は急速に低下してしまう(その兆候は認知症発症の数年前に現れる)。
なので,「脳年齢」というタームはワーキングメモリ能力に関しては便宜上使える(加齢と共に向上する脳機能や,加齢にほぼ無関係な脳機能には,脳年齢というタームは不適切だが)。
ワーキングメモリの脳内センターは前頭前野(前頭連合野)にあって,ワーキングメモリを使う課題をすると,若者に比べて高齢者ほど前頭前野を活性化させる。これは,若者ほど脳が効率的,ということが大きな要因になっている。より若いほどより少ないエネルギー(活性レベル)で脳を上手く使えるということである。
こうしたことから,ワーキングメモリとそれに関係する脳活動は「咬合療法による脳の若返り」を調べる上で適当な対象だと言える。
そこで,咬合療法によって1)ワーキングメモリ能力は向上するか?2)前頭前野の活性レベルは下がる
か?という二点を主に調べてきたのだが,結果は予想通りだった(図)。
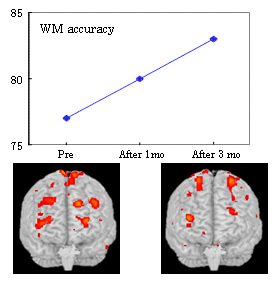
細かい話はブログの性質上端折るが,咬合療法によるワーキングメモリ能力の向上率は,「脳年齢」に換算すると平均しておよそ20歳に若返りに相当する。50歳なら30歳ほどの脳年齢になる,ということである。
これだけでも驚くが,咬合療法によってワーキングメモリ能力が向上すると同時に,前頭前野の活性レベルが下がることも判明した。咬合療法によって脳が効率化し脳が若返ることが示唆されるわけだ。
かくして,咬合療法は二重の意味で脳を若返させることになる(ワーキングメモリ能力の向上+脳の効率化)。
「加齢は脳によってコントロールされる」というのが,最近の脳科学での「常識」である。咬合是正によって身体が若返ることの主要因は脳の若返りにあると,私たちは考えている。
こうした研究成果が高齢化が急速に進む日本にあっていかに大きな意味をもつのかは,あえて言うまでもないだろう。
ただ,このような研究だけでも意味はあるものの,咬合療法による脳機能や脳活動(さらには脳構造や脳内ホルモン)への諸効果に関しては更なる研究が必要だと私はこれまでずっと考えていたし,今もそうだ。
そのため,ここで述べたようなことは一般向けには(日本咬合学会関係の市民向けフォーラムを除いて)あまり積極的に言及してこなかった。
ところが,昨今になって「似非咬合是正」「咬合療法まがい」とみなす他ないような方法や言説が増えているように思えてきたので,あえて述べた次第である。
なお,咬み合わせ・咬合是正の奥深さと広がりは,冒頭で述べたシンポジウムでかなり発信されたと思う。とくに,おおたわ史絵先生がシンポジストとして御出席なされたことは,色々な点で良かった。流石,おおたわ史絵先生,といった感じであった。
